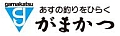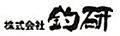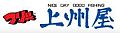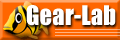台風一過! 時化後の荒食いって本当にあるのかなぁ~?
 観測史上最高の24時間降雨量を記録した台風6号が去り、東京湾では明日から釣船の出船が再開される。で、台風一過や大風のあとで必ず言われるのが「時化後の荒食い」。海が荒れた翌日、翌々日は魚の活性が高くなり爆釣フラグが立つというのであるが……本当なんだろうか?
観測史上最高の24時間降雨量を記録した台風6号が去り、東京湾では明日から釣船の出船が再開される。で、台風一過や大風のあとで必ず言われるのが「時化後の荒食い」。海が荒れた翌日、翌々日は魚の活性が高くなり爆釣フラグが立つというのであるが……本当なんだろうか?
 本当なんだろうか?と書いたのは、へた釣りは時化後の荒食いを実感したことがないから。船宿のサイトで「時化後の荒食いに期待!」と書いてあると、素直に期待してしまうのだが、釣果はいつも通りか、ウネリが残っている分釣りづらくっていつもより少し悪いような気も……。時化後の荒食いはウネリで客足が遠のくのを回避するための船宿の謀略?という気がしないでもない。
本当なんだろうか?と書いたのは、へた釣りは時化後の荒食いを実感したことがないから。船宿のサイトで「時化後の荒食いに期待!」と書いてあると、素直に期待してしまうのだが、釣果はいつも通りか、ウネリが残っている分釣りづらくっていつもより少し悪いような気も……。時化後の荒食いはウネリで客足が遠のくのを回避するための船宿の謀略?という気がしないでもない。
時化後の荒食いを理屈で証明するなら、以下のようになる。
1.海水が撹拌されるので水中の酸素の量が増えて魚の活性が上がる 海水が撹拌されている状態の方が一部の魚の活性が上がるというのは何度か経験がある。水深20メートルくらいを狙うLTアジなどがそうで、べた凪だと全く口を使ってくれなかったアジが風が強くなり、波が1.5メートルくらいになると急に入れ食いになったりする。6メートルの波と20メートルの風が吹いた台風6号の大時化はこれが大規模化したようなもので、もっと深い水深でも水中の酸素の量が増えて魚の活性が上がっているってことだろうか?
海水が撹拌されている状態の方が一部の魚の活性が上がるというのは何度か経験がある。水深20メートルくらいを狙うLTアジなどがそうで、べた凪だと全く口を使ってくれなかったアジが風が強くなり、波が1.5メートルくらいになると急に入れ食いになったりする。6メートルの波と20メートルの風が吹いた台風6号の大時化はこれが大規模化したようなもので、もっと深い水深でも水中の酸素の量が増えて魚の活性が上がっているってことだろうか?
2.大雨で川から大量の水が流れ込み濁りが入って活性上がる 台風の雨によって濁流となった川の水は当然、海に流れ込む。この川の水が海水に濁りと魚の餌となるプランクトンをもたらすから、時化後は魚の活性が上がるというのも理にかなっているような気がする。釣りの大敵は澄み潮。潮が澄んでてきれいだなぁっと思った日は釣果に恵まれたことがない。程よく濁った海水なら、魚の警戒心も薄れて爆釣フラグが立ちやすいのは間違いない。
台風の雨によって濁流となった川の水は当然、海に流れ込む。この川の水が海水に濁りと魚の餌となるプランクトンをもたらすから、時化後は魚の活性が上がるというのも理にかなっているような気がする。釣りの大敵は澄み潮。潮が澄んでてきれいだなぁっと思った日は釣果に恵まれたことがない。程よく濁った海水なら、魚の警戒心も薄れて爆釣フラグが立ちやすいのは間違いない。
3.時化の間捕食を我慢していた魚が一斉に餌を食べ始める ちょっと海が荒れ気味のとき、堤防などでは魚が波の影響を受けにくいストラクチャーの間とか、港の奥の方に退避している姿を見ることがある。目視で魚がじっとしたまま群れているのを確認できるので、試しに餌を入れてみたのだが……釣れない。魚は避難所では餌を食べないようである。とすると、2~3日時化が続いた後の魚は空腹なわけで、避難生活を脱した魚が荒食いに走るというのはあり得る話のような気がする。
ちょっと海が荒れ気味のとき、堤防などでは魚が波の影響を受けにくいストラクチャーの間とか、港の奥の方に退避している姿を見ることがある。目視で魚がじっとしたまま群れているのを確認できるので、試しに餌を入れてみたのだが……釣れない。魚は避難所では餌を食べないようである。とすると、2~3日時化が続いた後の魚は空腹なわけで、避難生活を脱した魚が荒食いに走るというのはあり得る話のような気がする。
時化後の荒食いを期待して釣行した人の釣行記をいくつか読んでみたのだが、釣れていたり、釣れてなかったり……あまり時化後だからという影響はないような気がする。それでも、「時化後の荒食い」を期待して釣りに行き、今日は釣れるはずという根拠が1つ増えたと喜ぶのが釣り人の心理のようなwww
最近の気になる魚・物・話題の記事
・土曜は初釣りで行き損ねた和彦丸キスアジリレー…雪だけど・田丸屋「瑞葵」超えチューブわさび「葵ノ頂 静岡本わさび」
・カイワリ刺し4匹分ドカ食い。この瞬間のために釣りしてる
・気付いてなかった!! デプスのビリケンルアーは絶対に買う
・カイワリに行くと決めたら五十肩きちゃったよ…ついてない
・今週末は凪っぽいのでカイワリ狙って伊豆での初釣りに行く
・容量60Lで6000円ならがまかつの防水トートバッグいいかも
・「リアランサー 中深場82 HH195」ならお金足りるんだけど
・禁煙11年生はお金貯まれば極鋭 CG P HHH-205AGSの#1かな
・分かっていたけど…極鋭 CG P HHH-205AGSの#1見つからず
・よしださんのビシアジ竿「MXM 豚鯵SPECIAL」気になるけど
・伊豆での初釣りの予定だったが時化でほぼ絶望的な気がする
・進化型釣りエサ「ハイブリッド クロス」はカイワリにどう?
・ブラシスレっダーってガイド掃除しながらライン通せるの?
・貸し竿のおかげで極鋭って凄いんだってことが今さら分かった
・仕舞寸22.5cmでちょい投げも「OUTBACK PUPPY」気になる
・アルファタックルの和竿テイスト「涼舟」シリーズがそそる
・初釣り2026はかみやからオニカサゴに決定♪ 目標は“吉”以上
・リール視点のアングルありかも!!と一瞬だけ考えてしまった
・本命ボウズ48日目に…初釣りはオニカサゴでいいんだろうか
・あ~~~~~~~~~~~まんくそ悪い。初釣りは来週だね
・渋谷から河口湖駅までバスで2時間。ドーム船でワカサギ!?
・初釣りは昨年流れたカイワリかおみくじ気分でオニカサゴか
・2026年はのっけからニンバス感染?でへろへろな年始に……
・世の中に何の影響もない2025年のへた釣り10大ニュースw
・シロアマは甘みの輪郭はっきり。酒蒸しはアマダイの方が○
・正月の雑煮にお餅の代わりに入れる紅白アマダイで釣り納め
・大漁祈願と商売繁盛祈願で元日は堀川戎神社に初詣に行こう
・「根魚」読み方はねざかな? ねうお? ねぎょ? こんぎょ?
・釣り納めのアマダイに向け〇金2個から大きいのを選んだよ
・釣餌用生しらすが復活したと思ったら1万7900円でびっくり
・カイワリプチ遠征2025第9戦は荒天強風のために出船中止に
・明日は雨中の2025年カイワリプチ遠征最終戦。ツ抜け目指す
・「快適天秤アーチ 1.8mm」がアマダイ用にバカによく見える
・あっ!! 間違えて出刃&柳刃包丁を頼んでしまった(棒読みw)
・2025年のへた釣りの漢字は「透」。はっきり見えるって大事
・メバル用のべ竿を置かせてもらえば倉橋島で釣りできるかも
・今年のバレンタインは「ブラックサンダールアー」が欲しい♪
・シマアジはビシカゴ表面をギンギラギンにするとよく釣れる?
・呉・倉橋島の秋の蠣筏釣りのターゲットはハゲことカワハギ
・お刺身用に包丁を1本買うなら身卸包丁がいいらしいのだが
・ナンヨウカイワリは三重では「シマアジのオバ」と呼ばれる
・「オシア」のスプール交換にいつもすごく苦戦…コツある?
・今年はひょっとして白間津シマアジ期待してええんちゃう?
・顏認証で入店し無人店舗で餌を購入「いつでもえさルア24H」
・2025年は残すは3戦。シマアジ、アマダイ…カイワリかな?
・え~~~~、とうとう今日の午前シロアマダイ写真なし??
・やや長軸で強度十分な真鯛針を探していると「カット真鯛」
・土曜の午後船空いてる…宇佐美でシロアマダイチャレンジ?
・盗られたくないものだけ東谷のタックルラックで室内で管理
著者: へた釣り