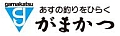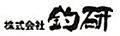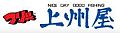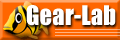食い渋りに細ハリス…魚って目はよくないって聞いたけど?
 ウキフカセでも船釣りでも、食い渋りのときは細ハリスが有利と言われる。釣りをする人が経験則から導き出した結論だし、実際、細ハリス+小針、小餌は効果を実感できることも多い。でも、魚って目が悪いって聞いたこともあるんだけど……見えないけど細い方がいい、その理由とは。
ウキフカセでも船釣りでも、食い渋りのときは細ハリスが有利と言われる。釣りをする人が経験則から導き出した結論だし、実際、細ハリス+小針、小餌は効果を実感できることも多い。でも、魚って目が悪いって聞いたこともあるんだけど……見えないけど細い方がいい、その理由とは。
 ウキフカセ釣りでは、対象の魚を自分の竿さばきで取り込める自信があるギリギリの細さのハリスを使うのが基本。大型のメジナ狙いだから2号のハリスを使いたいけど、食ってこないから1.2号に変えたらハリスが切れたなんて経験がある。ボートからのシロギス狙いでも1号のハリスを使っていたら全然魚信がなかったのに0.6号に仕掛けを変えたらバンバン食ってくるようになったなんてことも。
ウキフカセ釣りでは、対象の魚を自分の竿さばきで取り込める自信があるギリギリの細さのハリスを使うのが基本。大型のメジナ狙いだから2号のハリスを使いたいけど、食ってこないから1.2号に変えたらハリスが切れたなんて経験がある。ボートからのシロギス狙いでも1号のハリスを使っていたら全然魚信がなかったのに0.6号に仕掛けを変えたらバンバン食ってくるようになったなんてことも。
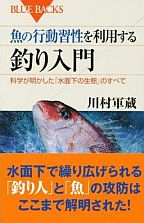 一方で魚の生態を解説した本を読むと、例外なく魚は目が悪いと書いてある。水中に棲む魚と人間の視力を比べることに意味はないかもしれないが、人間の視力の測定法を指標とするなら魚の視力は0.2以下。魚にハリスが見えるのは10センチくらいの至近に接近してからだと言われている。たとえハリスが見えたとしても、魚にとって「ハリス=危険」という認識があるとは思えない。ハリスが危険という認識が魚にあるなら、カワハギやフグなどのホバリングする魚は釣れないということになる。
一方で魚の生態を解説した本を読むと、例外なく魚は目が悪いと書いてある。水中に棲む魚と人間の視力を比べることに意味はないかもしれないが、人間の視力の測定法を指標とするなら魚の視力は0.2以下。魚にハリスが見えるのは10センチくらいの至近に接近してからだと言われている。たとえハリスが見えたとしても、魚にとって「ハリス=危険」という認識があるとは思えない。ハリスが危険という認識が魚にあるなら、カワハギやフグなどのホバリングする魚は釣れないということになる。
■針&ハリス付きの餌に違和感を抱かせないのが釣りの基本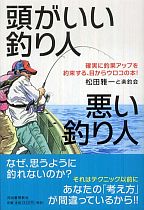 では、なぜ細ハリス? どうやら魚は対象物がボンヤリとしか見えていない一方で、対象物の動きが捕食対象のものであるか、どうかを鋭敏に察知する能力には長けているようだ。水中のハリスは抵抗である。自然に漂い沈下するオキアミなどの餌の動きを阻害する要因に過ぎない。極端な例にすると針金の先端に針を結んで餌を付けたところで、よほどのことがない限り魚は餌を食べない。メジナはコマセと同じように自然に沈下するオキアミになら飛びつくし、自然に海底を漂うイソメにシロギスの捕食スイッチが入る。
では、なぜ細ハリス? どうやら魚は対象物がボンヤリとしか見えていない一方で、対象物の動きが捕食対象のものであるか、どうかを鋭敏に察知する能力には長けているようだ。水中のハリスは抵抗である。自然に漂い沈下するオキアミなどの餌の動きを阻害する要因に過ぎない。極端な例にすると針金の先端に針を結んで餌を付けたところで、よほどのことがない限り魚は餌を食べない。メジナはコマセと同じように自然に沈下するオキアミになら飛びつくし、自然に海底を漂うイソメにシロギスの捕食スイッチが入る。
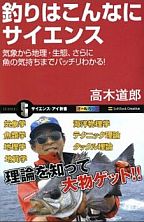 ボンヤリとしか見えてないものが、動きが自然なら餌に見える。ルアーはまさにこの魚の習性を利用した釣りだし、へた釣りが研究中のイサキのウィリー釣りも化繊巻き針をアミエビだと魚に見誤らせる釣りだ。もちろん、魚が餌を認識する方法には臭いや色という動き以外の要素もある。ウィリー釣りの場合、本物のアミエビをコマセとして撒くので臭いはOK。色はその日、その日によって当たりの化繊色があるようで、名人は、何種類もの色、それを何重に巻くかを変えた針をたっぷり準備して釣りに臨むものらしい。
ボンヤリとしか見えてないものが、動きが自然なら餌に見える。ルアーはまさにこの魚の習性を利用した釣りだし、へた釣りが研究中のイサキのウィリー釣りも化繊巻き針をアミエビだと魚に見誤らせる釣りだ。もちろん、魚が餌を認識する方法には臭いや色という動き以外の要素もある。ウィリー釣りの場合、本物のアミエビをコマセとして撒くので臭いはOK。色はその日、その日によって当たりの化繊色があるようで、名人は、何種類もの色、それを何重に巻くかを変えた針をたっぷり準備して釣りに臨むものらしい。
最近の気になる魚・物・話題の記事
・今週末は猿島沖の初釣りにいなの丸のビシアジに行ってくる・かみやのカサゴはブラクリOK。でもハタはもう少し暖かく?
・釣りをお休みすると五十肩が発症するから今週は絶対に行く
・湾奥出船のカサゴ船でブラクリで良型狙ったら怒られるかな
・ミズノのブレスサーモ発熱ミドラーがとても欲しくなってる
・雪雨マーク消えたから和彦丸予約したのに…やっぱり降るの?
・2026年も湾奥メバルは絶滅危惧種? 釣れても小さい感じ?
・土曜は初釣りで行き損ねた和彦丸キスアジリレー…雪だけど
・田丸屋「瑞葵」超えチューブわさび「葵ノ頂 静岡本わさび」
・カイワリ刺し4匹分ドカ食い。この瞬間のために釣りしてる
・気付いてなかった!! デプスのビリケンルアーは絶対に買う
・カイワリに行くと決めたら五十肩きちゃったよ…ついてない
・今週末は凪っぽいのでカイワリ狙って伊豆での初釣りに行く
・容量60Lで6000円ならがまかつの防水トートバッグいいかも
・「リアランサー 中深場82 HH195」ならお金足りるんだけど
・禁煙11年生はお金貯まれば極鋭 CG P HHH-205AGSの#1かな
・分かっていたけど…極鋭 CG P HHH-205AGSの#1見つからず
・よしださんのビシアジ竿「MXM 豚鯵SPECIAL」気になるけど
・伊豆での初釣りの予定だったが時化でほぼ絶望的な気がする
・進化型釣りエサ「ハイブリッド クロス」はカイワリにどう?
・ブラシスレっダーってガイド掃除しながらライン通せるの?
・貸し竿のおかげで極鋭って凄いんだってことが今さら分かった
・仕舞寸22.5cmでちょい投げも「OUTBACK PUPPY」気になる
・アルファタックルの和竿テイスト「涼舟」シリーズがそそる
・初釣り2026はかみやからオニカサゴに決定♪ 目標は“吉”以上
・リール視点のアングルありかも!!と一瞬だけ考えてしまった
・本命ボウズ48日目に…初釣りはオニカサゴでいいんだろうか
・あ~~~~~~~~~~~まんくそ悪い。初釣りは来週だね
・渋谷から河口湖駅までバスで2時間。ドーム船でワカサギ!?
・初釣りは昨年流れたカイワリかおみくじ気分でオニカサゴか
・2026年はのっけからニンバス感染?でへろへろな年始に……
・世の中に何の影響もない2025年のへた釣り10大ニュースw
・シロアマは甘みの輪郭はっきり。酒蒸しはアマダイの方が○
・正月の雑煮にお餅の代わりに入れる紅白アマダイで釣り納め
・大漁祈願と商売繁盛祈願で元日は堀川戎神社に初詣に行こう
・「根魚」読み方はねざかな? ねうお? ねぎょ? こんぎょ?
・釣り納めのアマダイに向け〇金2個から大きいのを選んだよ
・釣餌用生しらすが復活したと思ったら1万7900円でびっくり
・カイワリプチ遠征2025第9戦は荒天強風のために出船中止に
・明日は雨中の2025年カイワリプチ遠征最終戦。ツ抜け目指す
・「快適天秤アーチ 1.8mm」がアマダイ用にバカによく見える
・あっ!! 間違えて出刃&柳刃包丁を頼んでしまった(棒読みw)
・2025年のへた釣りの漢字は「透」。はっきり見えるって大事
・メバル用のべ竿を置かせてもらえば倉橋島で釣りできるかも
・今年のバレンタインは「ブラックサンダールアー」が欲しい♪
・シマアジはビシカゴ表面をギンギラギンにするとよく釣れる?
・呉・倉橋島の秋の蠣筏釣りのターゲットはハゲことカワハギ
・お刺身用に包丁を1本買うなら身卸包丁がいいらしいのだが
・ナンヨウカイワリは三重では「シマアジのオバ」と呼ばれる
・「オシア」のスプール交換にいつもすごく苦戦…コツある?
著者: へた釣り