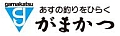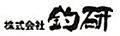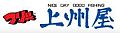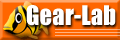所変われば魚の名も。ハゲ、ババタレ、チンチン、ガッチョ
 和歌山の堤防で釣りをしていると、後から来た釣り人に「釣れとるか?」と聞かれクーラーを開けると、「お、ええガシラとマルハゲやないか、このベラも美味しいんやで」。クーラーの中にいたのは、カサゴとカワハギ、ヒブダイ。「カサゴは入れ食いですよ」と言うと、「カサゴってガシラのことか?」
和歌山の堤防で釣りをしていると、後から来た釣り人に「釣れとるか?」と聞かれクーラーを開けると、「お、ええガシラとマルハゲやないか、このベラも美味しいんやで」。クーラーの中にいたのは、カサゴとカワハギ、ヒブダイ。「カサゴは入れ食いですよ」と言うと、「カサゴってガシラのことか?」
淡水魚の名前は琵琶湖周辺で呼ばれている名前で、海水魚は神奈川辺りで呼ばれている名前を標準和名として採用したという話を読んだことがある。元々、生のまま長距離移送する手段のなかった頃には魚の名前なんて、地元の人の間でそれと分かる名前が付けられていればよかったわけだ。釣りをする人には、一緒に釣りをする人の間で分かる呼称があればいいという考えが残っているようで、遠征先の釣り具屋で釣果を聞くと、聞き慣れない名前を当たり前のように聞くことになる。
 有名なことろではクロダイ。関西ではチヌ。九州ではチン。ここまでは覚えているとしてもこれに幼魚時代の名前が加わると、カイズになったり、チンチンになったり、メイタになったり。これに釣り人独特の呼称であるトシナシ、オオスケなんて呼び方が加わると、メイタってカレイ? オオスケって大型のスケトウダラ?とよく分からないことになる。
有名なことろではクロダイ。関西ではチヌ。九州ではチン。ここまでは覚えているとしてもこれに幼魚時代の名前が加わると、カイズになったり、チンチンになったり、メイタになったり。これに釣り人独特の呼称であるトシナシ、オオスケなんて呼び方が加わると、メイタってカレイ? オオスケって大型のスケトウダラ?とよく分からないことになる。
 メジナも関西ではグレ、九州ではクロと呼ばれるのだが、こちらはサイズによって名前が変わらないのでいくらか覚えやすい。サイズの違いは全国的にコッパ、手のひら、足裏、特大のものをチャ(茶)で通じるような気がする。サイズの呼び名+地方名でおおよそ通じる。コッパメジナ、足裏クロ、チャグレって感じ。尾長と口太は両種が混ざるポイントでは尾長グレ、口太メジナという具合に使い分ける。
メジナも関西ではグレ、九州ではクロと呼ばれるのだが、こちらはサイズによって名前が変わらないのでいくらか覚えやすい。サイズの違いは全国的にコッパ、手のひら、足裏、特大のものをチャ(茶)で通じるような気がする。サイズの呼び名+地方名でおおよそ通じる。コッパメジナ、足裏クロ、チャグレって感じ。尾長と口太は両種が混ざるポイントでは尾長グレ、口太メジナという具合に使い分ける。
 出世魚のせいで覚えにくいのが、全国的にシーバスで通じるようになったスズキやブリ。スズキは、関東ではセイゴ→フッコ→スズキ。関西だと. セイゴ→ハネ→スズキとなるのだが、生きエビを半殺しにして撒いて釣るハネ釣りが関西の堤防では盛んなので、ハネ釣りという名前をよく聞くことになる。ハネ釣りって名前だけを聞くとトビウオ釣りを想像したのはへた釣りだけ? ブリは関東ではワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ。関西ではツバス→ハマチ→メジロ→ブリ。東京の寿司屋でもハマチの握りは注文できるが……東京の人はブリの若魚だって認識してない? ハマチはブリの養殖物という誤解もあるような……。
出世魚のせいで覚えにくいのが、全国的にシーバスで通じるようになったスズキやブリ。スズキは、関東ではセイゴ→フッコ→スズキ。関西だと. セイゴ→ハネ→スズキとなるのだが、生きエビを半殺しにして撒いて釣るハネ釣りが関西の堤防では盛んなので、ハネ釣りという名前をよく聞くことになる。ハネ釣りって名前だけを聞くとトビウオ釣りを想像したのはへた釣りだけ? ブリは関東ではワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ。関西ではツバス→ハマチ→メジロ→ブリ。東京の寿司屋でもハマチの握りは注文できるが……東京の人はブリの若魚だって認識してない? ハマチはブリの養殖物という誤解もあるような……。
■釣り人独特な呼称が入ると……もう何が何やら分からない 釣り人だけで通用する魚の呼称が加わると、さらに何が何だか分からなくなる。メゴチは関西ではガッチョだ。関東ではこの魚を天ぷらにするのだが、関西ではヌルヌルするので嫌われており、リリースすらしてもらえず天日干しにされて干からびているのをよく見かける。逆に関東では嫌われもののキュウセンベラは関西ではギザミと呼ばれてキープされることが多い。アイゴはバリだし、ブダイはイガミ、キジハタはアコウ。北陸遠征すると、メバルはハチメと呼ばれていた。つい最近も伊豆で大きなカサゴを釣ったと思ったら船長から「カンコ」と説明される。沖にいるカサゴに似た魚のことを伊豆ではカンコと呼ぶらしい。
釣り人だけで通用する魚の呼称が加わると、さらに何が何だか分からなくなる。メゴチは関西ではガッチョだ。関東ではこの魚を天ぷらにするのだが、関西ではヌルヌルするので嫌われており、リリースすらしてもらえず天日干しにされて干からびているのをよく見かける。逆に関東では嫌われもののキュウセンベラは関西ではギザミと呼ばれてキープされることが多い。アイゴはバリだし、ブダイはイガミ、キジハタはアコウ。北陸遠征すると、メバルはハチメと呼ばれていた。つい最近も伊豆で大きなカサゴを釣ったと思ったら船長から「カンコ」と説明される。沖にいるカサゴに似た魚のことを伊豆ではカンコと呼ぶらしい。
 さらにはなかなか30センチを超えるサイズには出会えない魚の30センチ超級のことをヒジタタキと呼んだりする。大型のシロギスをそう呼ぶことが多いようだが、渓流で大きなイワナを釣ったときにもビジタタキと言われたので、シロギス限定の呼び名ではなさそう。ほかにもポン級は30センチを超えるアイナメがビール瓶に見えることから付けられた呼称だし、ザブトンは40センチを超えるカレイを、その上に座れそうなってことでそう呼ぶ。大きなシイラのことはファイトの強烈さからマンビキ(万引)なんて呼ぶことも。
さらにはなかなか30センチを超えるサイズには出会えない魚の30センチ超級のことをヒジタタキと呼んだりする。大型のシロギスをそう呼ぶことが多いようだが、渓流で大きなイワナを釣ったときにもビジタタキと言われたので、シロギス限定の呼び名ではなさそう。ほかにもポン級は30センチを超えるアイナメがビール瓶に見えることから付けられた呼称だし、ザブトンは40センチを超えるカレイを、その上に座れそうなってことでそう呼ぶ。大きなシイラのことはファイトの強烈さからマンビキ(万引)なんて呼ぶことも。
 この名前やだなという代表がババタレ。メジナ釣りのお邪魔虫、イスズミのことをそう呼んでいるのを聞いたことがあるのだが、これは釣りあげたあと、針を外そうとするとウンコを漏らすから付いた名前。同じような理由で名前がついた魚にはテカミハゼがいる。この魚は針を外そうとすると手に噛みついてくる。歯はないので痛くはないが、ちょっとびっくりさせられる。標準和名はイトヒキハゼ。釣り人が呼ぶ名前が分かっていても、標準和名が分からないこともある。北海道でガンズと呼ばれるギンポを凶悪にしたような魚……あれは一体なんて魚?
この名前やだなという代表がババタレ。メジナ釣りのお邪魔虫、イスズミのことをそう呼んでいるのを聞いたことがあるのだが、これは釣りあげたあと、針を外そうとするとウンコを漏らすから付いた名前。同じような理由で名前がついた魚にはテカミハゼがいる。この魚は針を外そうとすると手に噛みついてくる。歯はないので痛くはないが、ちょっとびっくりさせられる。標準和名はイトヒキハゼ。釣り人が呼ぶ名前が分かっていても、標準和名が分からないこともある。北海道でガンズと呼ばれるギンポを凶悪にしたような魚……あれは一体なんて魚?
最近の気になる魚・物・話題の記事
・関東は台風15号の直撃もあり? 土曜は行けても湾内限定?・ふるさと納税なら日本で設計された高品質バッテリー買える?
・たんぱく質制限のせいで釣りは休み休みになってしまうのよ
・新防寒着はモンベルが船釣り用に設計した「シーアングラー」
・最大25倍に拡大!! これなら船上で回転ビーズに枝ス通せる?
・眼鏡と偏光グラス、モバイルバッテリーも…まじで金欠かも
・夜メバルの荷造りしただけで汗が…移動中は熱中症に注意?
・メバル胴突き3本針作成時間3時間→20分。目が見えるの大事
・6月・7月の新島キンメは白子や真子が入って美味しいらしい
・暑くてひぃひぃ言ってるので今週末はリレーなしで夜メバル
・小型電動の予備機に「ELAN SW DENDO 100」がほしいかも!!
・もしかして猛暑でモバイルバッテリーも性能劣化している?
・白いGoPro HERO13 Black到着♪ 防水性維持し外部電源化も
・デカサゴ&ハタに色気出して夜メバクリって怒られるかな?
・365nmのアニサキスライトが今なら1000円(送料込み)で!!
・GoPro代稼がなきゃいけないのでお盆は釣り休んでお仕事を
・GoProの外部電源化と防水を両立するには「Contactoドア」
・熱のせい? 雨のせい? GoPro 8Blackが完全にお亡くなりに
・倍速でとはいわんが1.5倍速で仕掛け作れるようになったよ
・尿酸3.9で痛風なんて怖くない♪ 次はたんぱく質制限解除を
・今週末は久々に妻とアジ釣りデートに行ってくるよ~~~♪
・アクションカメラ用にちょうどいい冷却装置…見つからない
・回転ビーズに糸通る!!のがうれしいから復帰戦はシロギス!
・汚い手で目を擦らなければ釣り行ってOKとお許し出たよ~
・脂ノリノリ表面テカったデカイワリは無言になるほど旨い
・白内障手術前の釣り納めは一番食べたいカイワリに行くよ~
・魚はだいたい100gあたりたんぱく質20gと覚えておけばよい
・「食べきれないなら近所に配る」でキスアジリレーに行くよ
・そば切り うちばが品川シーサイド近くといまさら気付いた
・シロギスのテンビン仕掛けなら視力が0.2でも作れるかも?
・ん? 白内障手術後に眼鏡を作れるのは1カ月後? 釣りは?
・クールラインキャリーIIIが15Lとやや小型だけど気になるぞ
・白内障の手術&入院に向けで骨董品?なiPodを充電してみる
・カイワリ釣るのに金に糸目は付けない。生食用生しらす買う
・伊豆でサバ大不漁と知ってカイワリ釣りやすいとニンマリ!?
・散歩に行くと釣りに行く気が…体を労わってこなかったツケ
・仕事&仕掛け作りに単焦点か、穂先が見える2焦点かで悩む
・大阪でエギタコでロストしたエギとスッテを補給してきたよ
・今週末は大阪行きで…2025年はなかなか釣りに行けないのよ
・ヨロイイタチウオの酒蒸しはアマダイを超えてる気がするぞ
・アカムツ狙いで最後までが希望だが一応アラの釣り方を予習
・5年以上ぶりの2日連荘で稲取アカムツ→東京湾エギダコに!!
・食べきれないなら釣るなと言われると釣りお休みになるかも
・痛風危機が去ったら今度はたんぱく質の摂取量制限くらう?
・かみやのマダコ初日は44人中32人がツ抜けで期待してよい?
・シラス不漁の影響? 釣り餌用冷凍生しらすが長期売り切れ
・かみやのエギタコ新釣法は豚肉だけでなくネギも巻くらしいw
・最近起きている悪循環。視力低下→仕事遅い→釣り行けない
・夏のカイワリは抜群!! 博多風ごまあじも期待以上の旨さで
・シーズン初期のマダコはエギを小さくした方がいいのかな?
著者: へた釣り