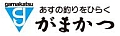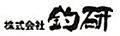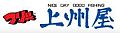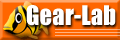定住性の高いカサゴなのに大型だけ行方不明ってあるの?
 とにかくキープサイズに恵まれなかったメバル開幕戦2015。メバルはハリスを見切って口を使ってこないってことはあるにしても、目の前にエサがあれば必ずといっていいほど飛びついてくるカサゴが行方不明ってどういうことだろう? 特に大きなカサゴは船中で1匹もあがってなかった。
とにかくキープサイズに恵まれなかったメバル開幕戦2015。メバルはハリスを見切って口を使ってこないってことはあるにしても、目の前にエサがあれば必ずといっていいほど飛びついてくるカサゴが行方不明ってどういうことだろう? 特に大きなカサゴは船中で1匹もあがってなかった。
 根魚であるメバルとカサゴは1日の移動距離は最大で200メートル程度とされている。カサゴに至っては1キロ以内の範囲で一生を過ごすとも言われている。釣り尽くしてしまったという状況でない限り、カサゴは大きいのも小さいのも絶対に1キロ以内にいるのである。これが堤防やテトラなら、前に入った人が釣り尽くしてしまったってこともあるのだろうが、川崎~海堡までいろんなポイントを探ってみて、良型カサゴは1匹も姿を見ずとなると、どうして?と考えてみたくもなる。
根魚であるメバルとカサゴは1日の移動距離は最大で200メートル程度とされている。カサゴに至っては1キロ以内の範囲で一生を過ごすとも言われている。釣り尽くしてしまったという状況でない限り、カサゴは大きいのも小さいのも絶対に1キロ以内にいるのである。これが堤防やテトラなら、前に入った人が釣り尽くしてしまったってこともあるのだろうが、川崎~海堡までいろんなポイントを探ってみて、良型カサゴは1匹も姿を見ずとなると、どうして?と考えてみたくもなる。
 水温が低くなると影響を受けやすい堤防周りの浅場からカサゴが姿を消すという経験は伊豆で何度かしているが、東京湾の水温は10.5度くらいと安定している。生息する水深を変えたとは考えにくいし、30メートル近い深場も攻めているので、深い場所に移動していても捕捉できたはず。「潮が動かない時はメバルは口を使わずカサゴも釣れるのは小型が多い」という説を見つけた。瀬戸内海でメバル・カサゴ船を出しているからこと丸の船長さんの言なので、大型が出なかった理由はこれかな? 開幕戦の潮は小潮だった。
水温が低くなると影響を受けやすい堤防周りの浅場からカサゴが姿を消すという経験は伊豆で何度かしているが、東京湾の水温は10.5度くらいと安定している。生息する水深を変えたとは考えにくいし、30メートル近い深場も攻めているので、深い場所に移動していても捕捉できたはず。「潮が動かない時はメバルは口を使わずカサゴも釣れるのは小型が多い」という説を見つけた。瀬戸内海でメバル・カサゴ船を出しているからこと丸の船長さんの言なので、大型が出なかった理由はこれかな? 開幕戦の潮は小潮だった。
 潮回りが小さいと大型のカサゴが釣れない理由というのが、どうにも分からない。カサゴは目の前にエサがあれば確実に食いついてくるという認識は、小型のカサゴには当てはまるが大型のカサゴには当てはまらない? それとも潮が緩いとエサをカサゴの住処に送り込みにくくなる? でも、それじゃ小型ならいくらでも釣れて大型だけ釣れないという説明がつかない。海底での潜み方が小型と大型では違うのか? 釣り慣れた魚のはずなのに意外と奥が深いかも。
潮回りが小さいと大型のカサゴが釣れない理由というのが、どうにも分からない。カサゴは目の前にエサがあれば確実に食いついてくるという認識は、小型のカサゴには当てはまるが大型のカサゴには当てはまらない? それとも潮が緩いとエサをカサゴの住処に送り込みにくくなる? でも、それじゃ小型ならいくらでも釣れて大型だけ釣れないという説明がつかない。海底での潜み方が小型と大型では違うのか? 釣り慣れた魚のはずなのに意外と奥が深いかも。
最近の気になる魚・物・話題の記事
・伊豆での初釣りの予定だったが時化でほぼ絶望的な気がする・進化型釣りエサ「ハイブリッド クロス」はカイワリにどう?
・ブラシスレっダーってガイド掃除しながらライン通せるの?
・貸し竿のおかげで極鋭って凄いんだってことが今さら分かった
・仕舞寸22.5cmでちょい投げも「OUTBACK PUPPY」気になる
・アルファタックルの和竿テイスト「涼舟」シリーズがそそる
・初釣り2026はかみやからオニカサゴに決定♪ 目標は“吉”以上
・リール視点のアングルありかも!!と一瞬だけ考えてしまった
・本命ボウズ48日目に…初釣りはオニカサゴでいいんだろうか
・あ~~~~~~~~~~~まんくそ悪い。初釣りは来週だね
・渋谷から河口湖駅までバスで2時間。ドーム船でワカサギ!?
・初釣りは昨年流れたカイワリかおみくじ気分でオニカサゴか
・2026年はのっけからニンバス感染?でへろへろな年始に……
・世の中に何の影響もない2025年のへた釣り10大ニュースw
・シロアマは甘みの輪郭はっきり。酒蒸しはアマダイの方が○
・正月の雑煮にお餅の代わりに入れる紅白アマダイで釣り納め
・大漁祈願と商売繁盛祈願で元日は堀川戎神社に初詣に行こう
・「根魚」読み方はねざかな? ねうお? ねぎょ? こんぎょ?
・釣り納めのアマダイに向け〇金2個から大きいのを選んだよ
・釣餌用生しらすが復活したと思ったら1万7900円でびっくり
・カイワリプチ遠征2025第9戦は荒天強風のために出船中止に
・明日は雨中の2025年カイワリプチ遠征最終戦。ツ抜け目指す
・「快適天秤アーチ 1.8mm」がアマダイ用にバカによく見える
・あっ!! 間違えて出刃&柳刃包丁を頼んでしまった(棒読みw)
・2025年のへた釣りの漢字は「透」。はっきり見えるって大事
・メバル用のべ竿を置かせてもらえば倉橋島で釣りできるかも
・今年のバレンタインは「ブラックサンダールアー」が欲しい♪
・シマアジはビシカゴ表面をギンギラギンにするとよく釣れる?
・呉・倉橋島の秋の蠣筏釣りのターゲットはハゲことカワハギ
・お刺身用に包丁を1本買うなら身卸包丁がいいらしいのだが
・ナンヨウカイワリは三重では「シマアジのオバ」と呼ばれる
・「オシア」のスプール交換にいつもすごく苦戦…コツある?
・今年はひょっとして白間津シマアジ期待してええんちゃう?
・顏認証で入店し無人店舗で餌を購入「いつでもえさルア24H」
・2025年は残すは3戦。シマアジ、アマダイ…カイワリかな?
・え~~~~、とうとう今日の午前シロアマダイ写真なし??
・やや長軸で強度十分な真鯛針を探していると「カット真鯛」
・土曜の午後船空いてる…宇佐美でシロアマダイチャレンジ?
・盗られたくないものだけ東谷のタックルラックで室内で管理
・アマダイでソコイトヨリが釣れたらタナは合ってるのかな?
・宇佐美沖でアラフィフ熟シロアマダイ釣れててうずうずする
・三度目の正直で今度こそミドフォー熟アマダイに癒されたい
・FLビシの「F」は船宿って意味だと16年も使ってやっと知る
・豚アジ刺し…もう大きすぎるアジは脂の乗りがとは言わない
・バッテリーを背負ってるから電熱ネックウォーマーありかも
・枝スは長くても15センチまで派だが豚アジにも通用するかな
・釜ごとご飯借りるほど美味しい!?「カマガリ」ことクログチ
・晴れの初島沖は夕マヅメのボーナスありで曇るとなしなの?
・ジャミサバの“ジャミ”って語源はなんだろうと調べてみたよ
・ビシのオモリって結構なバラツキがある? それとも削れた?
著者: へた釣り