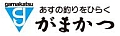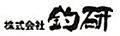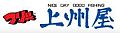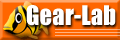聞いているタイミングで魚信を出すのが胴突きシロギスの肝
 あまりいろんなことを同時に考えると頭も体もついていかないので、「この釣りの肝はコレ」と言語化できた1つのことに集中して釣り方を詰めていくことにしている。シロギス釣りの肝は何?とずっと悩んでいたが、たっくん名人から「聞いているタイミングで魚信を出す」と教わり、得心する。
あまりいろんなことを同時に考えると頭も体もついていかないので、「この釣りの肝はコレ」と言語化できた1つのことに集中して釣り方を詰めていくことにしている。シロギス釣りの肝は何?とずっと悩んでいたが、たっくん名人から「聞いているタイミングで魚信を出す」と教わり、得心する。
 名人さんたちはもっといろいろなことを考えて釣っているのだろうが、へた釣りはいろんなことを考えなくてはならないレベルに達していない場合、まずその釣りの肝要は何だろうと考えることにしている。最も大事なことさえ分かれば、釣果がそれなりにまとまるようになり人並みには釣れるようになる。人並みに釣れるようになればその釣りが楽しくなって、もっと釣るためのあれこれにも気付くようになってくる。肝要をつかみ切れていない釣りはいくつかあるが、シロギスは15年前にデビューしたにも関わらず、な~んにもつかめていない。
名人さんたちはもっといろいろなことを考えて釣っているのだろうが、へた釣りはいろんなことを考えなくてはならないレベルに達していない場合、まずその釣りの肝要は何だろうと考えることにしている。最も大事なことさえ分かれば、釣果がそれなりにまとまるようになり人並みには釣れるようになる。人並みに釣れるようになればその釣りが楽しくなって、もっと釣るためのあれこれにも気付くようになってくる。肝要をつかみ切れていない釣りはいくつかあるが、シロギスは15年前にデビューしたにも関わらず、な~んにもつかめていない。
 白内障手術明け第一戦はシロギスご機嫌で自己最多の75匹♪で同船したシーバス師匠ことたっくん名人から帰港時にシロギス釣りに関する考え方を教えていただいた。胴突き仕掛けの場合、たるませて、張って、誘いを兼ねて聞く。ここまでは合っていたが魚信を出そうと狙っているタイミングが全く違った。へた釣りは仕掛けを海中でたるませているときにシロギスが餌を吸い込んで魚信が出るものだと思っていた。これが間違いで魚信をだすのは張っている最中か聞いている間であるべきだと知る。張っている最中に魚信が出れば聞く動作に移行して掛けにいく。聞いている最中に魚信がでれば難しいことを考えなくても掛かってくれる。
白内障手術明け第一戦はシロギスご機嫌で自己最多の75匹♪で同船したシーバス師匠ことたっくん名人から帰港時にシロギス釣りに関する考え方を教えていただいた。胴突き仕掛けの場合、たるませて、張って、誘いを兼ねて聞く。ここまでは合っていたが魚信を出そうと狙っているタイミングが全く違った。へた釣りは仕掛けを海中でたるませているときにシロギスが餌を吸い込んで魚信が出るものだと思っていた。これが間違いで魚信をだすのは張っている最中か聞いている間であるべきだと知る。張っている最中に魚信が出れば聞く動作に移行して掛けにいく。聞いている最中に魚信がでれば難しいことを考えなくても掛かってくれる。
 シロギス釣りの肝要は「聞いているタイミングでいかに魚信を出すか」と考えるとよさそう。聞いている最中にちょうどシロギスが餌をくわえるように、どれくらいたるませるか、たるませた状態で何秒待つかを試行錯誤していく。へた釣りは20秒たるませていたが長すぎたようだ。そう教わると、プルルと手元に伝わってくる魚信はあるのに2~3割しか掛からないと悩み続けてきたことがこの釣りの肝要を理解できてなかったからだと分かる。たるませている最中の魚信は、掛かることもあるが掛からないことの方が多いそうだ。「聞いているタイミングで魚信を出す」ように試行錯誤していけば、何かが見えてくる気がする。
シロギス釣りの肝要は「聞いているタイミングでいかに魚信を出すか」と考えるとよさそう。聞いている最中にちょうどシロギスが餌をくわえるように、どれくらいたるませるか、たるませた状態で何秒待つかを試行錯誤していく。へた釣りは20秒たるませていたが長すぎたようだ。そう教わると、プルルと手元に伝わってくる魚信はあるのに2~3割しか掛からないと悩み続けてきたことがこの釣りの肝要を理解できてなかったからだと分かる。たるませている最中の魚信は、掛かることもあるが掛からないことの方が多いそうだ。「聞いているタイミングで魚信を出す」ように試行錯誤していけば、何かが見えてくる気がする。
最近の釣りのお勉強記事
・夜メバルで来年振り出しに戻らないための内容の薄い備忘録・聞いているタイミングで魚信を出すのが胴突きシロギスの肝
・意図せずクロムツとシロムツの釣り分けに成功してるのだが
・ブラクリの自作は超簡単。でもどうしてPEで作るんだろう?
・ほぼ尺記念♪にイワシメバルのこうかな?メモを残しておく
・フグには海津針。多動性には短ハリス。アマダイ釣り小ネタ
・来年こそは釣りたいな~っと新島キンメのソレダメ!忘備録
・仮説と検証が釣りの楽しみ。カイワリング実験はまだ続くよ
・シロギス胴突きはタルマセ→シャクリだけの方が誘える?
・来年こそ40Upを釣りたい。萬栄丸・半夜クロムツ備忘録
・ウィリー+土佐カブラのハイブリッドでカイワリング2.0に
・本線に結びコブを作らないで強度保つ枝ス三方編み込み改
・良型率100%(今のところ)の土佐カブラのカイワリング
・目標尺超え!! イワシメバル初体験に向け釣り方を調べる
・目指せ半束…エビメバル手返し向上作戦を真剣に考えよう
・ビギナー多数の激混みアジ攻略は短仕掛けと声かけかな
・珍しく二連続で釣れた♪から長ハリスコマセマダイの備忘録
・細ハリスクッションなしイサキはドラグにおまかせが正解?
・群れが出入りする久里浜イサキはタナ決め打ちで粘り強く
・女子のコマセ振りはちゃんと片手をリールの前に添えて2回
・次こそツ抜けを! ヤリイカ釣行1回こっきりの人の備忘録
・初めてのLTアジ(コマセ)釣りで覚えてから行くべき8つの事
・クロムツ釣りは一度目の前にエサを通してから落として誘う
・剣崎イサキが超低活性時にはシャクらない・教えない作戦
・遠征ウィリーで魚種限定なのは枝ス5センチだったせいかも
・眉に唾少なめでOK。へた釣り印のカイワリ実績あり仕掛け
・イシダイの聞き上げは本当に竿を持ち上げるだけでよいのか
・きっとまた行く! 久里浜沖イシダイ五目の釣り方の備忘録
・マダイ釣りでクロダイ釣れたらタナを1メートル上げるが定石
・釣行後ほんの5分のひと手間でPEラインの寿命が半永久に
・災害級の暑さでも元気に釣りできる猛暑対策グッズまとめ
・糸の結び方は3つ覚えておけばマグロ釣らなければ大丈夫
・潮が速い日のアジに名人秘伝の脱力系フワフワ誘いを試す
・カイワリだけを選んで釣れた!! チダイは釣り方分からない!?
・仕掛け強度を上げるため添え糸なし枝ス編み付けを覚える
・動かさないウィリーの方にイサキが食ってくる条件を妄想す
・考えだすとハマるので考えたくはない枝スの長さの最適解
・ヒラメに味を占め来季もきっとやる。八景沖アミ五目備忘録
・潮の速さと仕掛け長、ソウダ禍の相関に悩んだイサキ2018
・剣崎沖イサキでソウダガツオ対策に効果抜群の超短仕掛け
・コマセ釣りは大潮を避ける。流して釣る底棲魚は大潮が○
・初島沖イサキは長ハリスがウィリーより3倍有利と認めるよ
・クロムツ狙いで底からオモリを10mは探る範囲が広すぎた!?
・もう1戦するかっ!! 多動性中年向けオニカサゴ誘い方メモ
・やらないのと知らないのは大違い。マダイの誘い方を調べる
・束釣り記念。えっへんおっほん気分でLTアジ愚策あれこれ
・剣崎沖イサキ2017総括。枝間は50センチ、ハンドルは大事
・イサキの追い食いは仕掛けの張りを意識してゆっくりと巻く
・バルーンサビキに餌が主流? シシャモは7月後半に接岸?
・今秋? 来春?から伝説を始める…深場のこうかな?メモ
著者: へた釣り