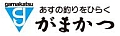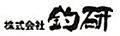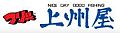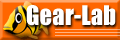師匠がくれたウィリー自作のヒントをへたなりに咀嚼してみる
 自作ウィリーで臨んだ剣崎沖イサキ第6戦も玉砕し、週末アングラーにはイサキが釣れないなんて無茶な屁理屈までこね出して、今年はイサキ釣りやめとけばいいのにって状態になっているのだが……やめられない。師匠からウィリー自作のヒントをもらったので紹介する。
自作ウィリーで臨んだ剣崎沖イサキ第6戦も玉砕し、週末アングラーにはイサキが釣れないなんて無茶な屁理屈までこね出して、今年はイサキ釣りやめとけばいいのにって状態になっているのだが……やめられない。師匠からウィリー自作のヒントをもらったので紹介する。
師匠の書いていることは分かることもあるし、分からないこともあるので、分かった部分だけ咀嚼してみると、以下の5つの法則が導き出される。
1.狙う魚ごとにシャクリ方の違いがあるので使い分ける ピッチの短いシャクリと、制止時間の短い止めでシマダイ。ロングピッチのシャクリと、長めの止めでマダイ。イサキはマダイのシャクリ方と似ているそうなのだが、止めはマダイほど長くとる必要はなく、以前「30秒止めている」と話すと「あり得ない」と言われたので、長くても10秒以下何だと思う。
ピッチの短いシャクリと、制止時間の短い止めでシマダイ。ロングピッチのシャクリと、長めの止めでマダイ。イサキはマダイのシャクリ方と似ているそうなのだが、止めはマダイほど長くとる必要はなく、以前「30秒止めている」と話すと「あり得ない」と言われたので、長くても10秒以下何だと思う。
2.水中でのウィリーのシルエットの見え方を想像する 水中では赤や茶(濃茶)は黒っぽく見え、白やピンクは淡く見えるものらしい。赤や茶(濃茶)は魚の目にシルエットがはっきり見え、白やピンクはシルエットがあいまいに見える。水深が深くなるほど、濁りや潮色が暗いほど、白やピンクが有利で、濁った水中で膨張して見える色なので、視認性が悪い環境の中では比較的認知しやすい。イサキには緑がいいというのは、緑のウィリーが中間色で特に際立った個性がないからだという。
水中では赤や茶(濃茶)は黒っぽく見え、白やピンクは淡く見えるものらしい。赤や茶(濃茶)は魚の目にシルエットがはっきり見え、白やピンクはシルエットがあいまいに見える。水深が深くなるほど、濁りや潮色が暗いほど、白やピンクが有利で、濁った水中で膨張して見える色なので、視認性が悪い環境の中では比較的認知しやすい。イサキには緑がいいというのは、緑のウィリーが中間色で特に際立った個性がないからだという。
3.針の地色はウイリーのコントラストで使い分ける 師匠にもらったウィリー針には、針が金のもの、銀のもの、オキアミカラーのものが混ざっていた。金と銀は潮色と釣れる層で使い分けるものらしい。逆にオキアミやホワイト針は針の存在を目立たせたくないときに使う。地の色とウイリーのコントラストで、仕掛け自体のアピール度をコントロールできるというのだが……。
師匠にもらったウィリー針には、針が金のもの、銀のもの、オキアミカラーのものが混ざっていた。金と銀は潮色と釣れる層で使い分けるものらしい。逆にオキアミやホワイト針は針の存在を目立たせたくないときに使う。地の色とウイリーのコントラストで、仕掛け自体のアピール度をコントロールできるというのだが……。
4.海の状況を把握するパイロットウィリーでまずは釣る 海中の状況をいちはやく察知するためのウィリーのセットをまずが作るべきというのが師匠のアドバイス。淡い色がいいのか、濃い色がいいのか、潮色はどうか、魚の群れは縦に伸びているのか、一か所に固まっているのか、針を目立たせるべきか目立たせないほうがいいのか。当日のアタリウィリーを探すためにいろんな色を混ぜたウィリー仕掛けを用意する。アタリウィリーが絞り込めたら、同系のウイリーを中心に組んだ仕掛けで勝負。釣れなくなったら、再び色混在のパイロットウィリーで新しい条件を探るといいようだ。
海中の状況をいちはやく察知するためのウィリーのセットをまずが作るべきというのが師匠のアドバイス。淡い色がいいのか、濃い色がいいのか、潮色はどうか、魚の群れは縦に伸びているのか、一か所に固まっているのか、針を目立たせるべきか目立たせないほうがいいのか。当日のアタリウィリーを探すためにいろんな色を混ぜたウィリー仕掛けを用意する。アタリウィリーが絞り込めたら、同系のウイリーを中心に組んだ仕掛けで勝負。釣れなくなったら、再び色混在のパイロットウィリーで新しい条件を探るといいようだ。
5.アミエビの生物臭を利用してウィリーに食いつかせる 師匠は徹底して、コマセの撒きすぎ厳禁派である。アミエビは生物臭を利用して、アミエビにウィリーの存在を気づかせるためにほんの少量撒くもの。あとはコマセの存在に気付いた魚をウィリーの不自然な動きで反射的に食わせるというのがこの釣りの醍醐味らしい。つまりコマセは魚を寄せるためのものではないってことみたいだ。魚が思わず食いつきたくなる色と動きで、コマセにではなくウィリーに飛びつかせるのが楽しいだという。
師匠は徹底して、コマセの撒きすぎ厳禁派である。アミエビは生物臭を利用して、アミエビにウィリーの存在を気づかせるためにほんの少量撒くもの。あとはコマセの存在に気付いた魚をウィリーの不自然な動きで反射的に食わせるというのがこの釣りの醍醐味らしい。つまりコマセは魚を寄せるためのものではないってことみたいだ。魚が思わず食いつきたくなる色と動きで、コマセにではなくウィリーに飛びつかせるのが楽しいだという。
最近の釣りのお勉強記事
・夜メバルで来年振り出しに戻らないための内容の薄い備忘録・聞いているタイミングで魚信を出すのが胴突きシロギスの肝
・意図せずクロムツとシロムツの釣り分けに成功してるのだが
・ブラクリの自作は超簡単。でもどうしてPEで作るんだろう?
・ほぼ尺記念♪にイワシメバルのこうかな?メモを残しておく
・フグには海津針。多動性には短ハリス。アマダイ釣り小ネタ
・来年こそは釣りたいな~っと新島キンメのソレダメ!忘備録
・仮説と検証が釣りの楽しみ。カイワリング実験はまだ続くよ
・シロギス胴突きはタルマセ→シャクリだけの方が誘える?
・来年こそ40Upを釣りたい。萬栄丸・半夜クロムツ備忘録
・ウィリー+土佐カブラのハイブリッドでカイワリング2.0に
・本線に結びコブを作らないで強度保つ枝ス三方編み込み改
・良型率100%(今のところ)の土佐カブラのカイワリング
・目標尺超え!! イワシメバル初体験に向け釣り方を調べる
・目指せ半束…エビメバル手返し向上作戦を真剣に考えよう
・ビギナー多数の激混みアジ攻略は短仕掛けと声かけかな
・珍しく二連続で釣れた♪から長ハリスコマセマダイの備忘録
・細ハリスクッションなしイサキはドラグにおまかせが正解?
・群れが出入りする久里浜イサキはタナ決め打ちで粘り強く
・女子のコマセ振りはちゃんと片手をリールの前に添えて2回
・次こそツ抜けを! ヤリイカ釣行1回こっきりの人の備忘録
・初めてのLTアジ(コマセ)釣りで覚えてから行くべき8つの事
・クロムツ釣りは一度目の前にエサを通してから落として誘う
・剣崎イサキが超低活性時にはシャクらない・教えない作戦
・遠征ウィリーで魚種限定なのは枝ス5センチだったせいかも
・眉に唾少なめでOK。へた釣り印のカイワリ実績あり仕掛け
・イシダイの聞き上げは本当に竿を持ち上げるだけでよいのか
・きっとまた行く! 久里浜沖イシダイ五目の釣り方の備忘録
・マダイ釣りでクロダイ釣れたらタナを1メートル上げるが定石
・釣行後ほんの5分のひと手間でPEラインの寿命が半永久に
・災害級の暑さでも元気に釣りできる猛暑対策グッズまとめ
・糸の結び方は3つ覚えておけばマグロ釣らなければ大丈夫
・潮が速い日のアジに名人秘伝の脱力系フワフワ誘いを試す
・カイワリだけを選んで釣れた!! チダイは釣り方分からない!?
・仕掛け強度を上げるため添え糸なし枝ス編み付けを覚える
・動かさないウィリーの方にイサキが食ってくる条件を妄想す
・考えだすとハマるので考えたくはない枝スの長さの最適解
・ヒラメに味を占め来季もきっとやる。八景沖アミ五目備忘録
・潮の速さと仕掛け長、ソウダ禍の相関に悩んだイサキ2018
・剣崎沖イサキでソウダガツオ対策に効果抜群の超短仕掛け
・コマセ釣りは大潮を避ける。流して釣る底棲魚は大潮が○
・初島沖イサキは長ハリスがウィリーより3倍有利と認めるよ
・クロムツ狙いで底からオモリを10mは探る範囲が広すぎた!?
・もう1戦するかっ!! 多動性中年向けオニカサゴ誘い方メモ
・やらないのと知らないのは大違い。マダイの誘い方を調べる
・束釣り記念。えっへんおっほん気分でLTアジ愚策あれこれ
・剣崎沖イサキ2017総括。枝間は50センチ、ハンドルは大事
・イサキの追い食いは仕掛けの張りを意識してゆっくりと巻く
・バルーンサビキに餌が主流? シシャモは7月後半に接岸?
・今秋? 来春?から伝説を始める…深場のこうかな?メモ
著者: へた釣り