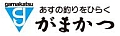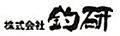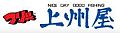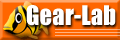カワハギ釣りの楽しみの1つ。集魚効果を期待し下錘を変える
 カワハギは好奇心の強い魚だと言われる。水中にキラキラ光るものに興味を示して寄ってくる。このため集寄板やビーズ状の中錘が使う人がいる。へた釣りは魚信が取りにくくなる集寄を使うのを今年から止めた。代わりに集魚効果を期待し下錘を頻繁(気分転換ともいう)に変えるように。
カワハギは好奇心の強い魚だと言われる。水中にキラキラ光るものに興味を示して寄ってくる。このため集寄板やビーズ状の中錘が使う人がいる。へた釣りは魚信が取りにくくなる集寄を使うのを今年から止めた。代わりに集魚効果を期待し下錘を頻繁(気分転換ともいう)に変えるように。
 カワハギが光るものに寄ってくるというのは釣り人が長年培ってきたノウハウなので、間違いない。でも大きくて水の抵抗の大きい集寄板や中錘を付けるとカワハギの魚信が小さいときにことごとく餌だけ取られるという経験を何度かした。魚信を察知するのに邪魔になる針より上の錘はタルマセたりハワセたりするときに海流に負けずに沈んでくれ
カワハギが光るものに寄ってくるというのは釣り人が長年培ってきたノウハウなので、間違いない。でも大きくて水の抵抗の大きい集寄板や中錘を付けるとカワハギの魚信が小さいときにことごとく餌だけ取られるという経験を何度かした。魚信を察知するのに邪魔になる針より上の錘はタルマセたりハワセたりするときに海流に負けずに沈んでくれ る重さがあれば十分というように考えるようになった。潮の流れが緩いときは0.8号、潮の流れが速いときは1.5号のワンタッチシンカーRを先糸のサルカン近くに打つだけにしている。竿を閃迅カワハギに変えたこともあった、これで取れる魚信(カワハギ以外も含む)は飛躍的に伸びたように感じる。
る重さがあれば十分というように考えるようになった。潮の流れが緩いときは0.8号、潮の流れが速いときは1.5号のワンタッチシンカーRを先糸のサルカン近くに打つだけにしている。竿を閃迅カワハギに変えたこともあった、これで取れる魚信(カワハギ以外も含む)は飛躍的に伸びたように感じる。
■浅場は赤、ピンクで反射板付き。深場は発光・夜光で
 中錘に集魚効果を期待できなくなった分、下錘でカワハギを寄せたいと考える。へた釣りは釣り具店のカワハギコーナーに立ち寄るたびになぜか錘を数個ずつ手に取るようになっている。一番よく使うのは、錘に反射板が付いたタイプで小さな集寄板代わりになりそうなもの。水深が浅い場合は、赤やピンク、黒などの水中で反射板だけが目立ちそうな色の錘を使っている。カジ付きというタイプもときどき使う。
中錘に集魚効果を期待できなくなった分、下錘でカワハギを寄せたいと考える。へた釣りは釣り具店のカワハギコーナーに立ち寄るたびになぜか錘を数個ずつ手に取るようになっている。一番よく使うのは、錘に反射板が付いたタイプで小さな集寄板代わりになりそうなもの。水深が浅い場合は、赤やピンク、黒などの水中で反射板だけが目立ちそうな色の錘を使っている。カジ付きというタイプもときどき使う。
 水深が深めで30メートル以深の場合は、錘を夜光や発光タイプに変えるようにしている。ルミコなどの発光体を付けてカワハギを狙う人もいるように、光が届きにくい深場では、カワハギは光に寄ってくるはずだと想像している。一応、反射板付き、目玉付きを持っているが反射する煌めきよりも錘全体が光るって方が大事だと思う。
水深が深めで30メートル以深の場合は、錘を夜光や発光タイプに変えるようにしている。ルミコなどの発光体を付けてカワハギを狙う人もいるように、光が届きにくい深場では、カワハギは光に寄ってくるはずだと想像している。一応、反射板付き、目玉付きを持っているが反射する煌めきよりも錘全体が光るって方が大事だと思う。
■混んでる船では無垢もアリ。六角・丸型は気分次第
 一応、無垢の錘も持っていく。これは「集魚効果ばかり狙った錘が底にいっぱい並んでいるとカワハギがスレることがある」と聞いたことがあるからだ。使用頻度は高くはないが、混んでいる船で使うと確かに集魚錘を使うよりも有利という局面があるように感じる。セコい話だが、根掛かりが多くて高価な集魚錘を使うのがもったいないというときにも使う。
一応、無垢の錘も持っていく。これは「集魚効果ばかり狙った錘が底にいっぱい並んでいるとカワハギがスレることがある」と聞いたことがあるからだ。使用頻度は高くはないが、混んでいる船で使うと確かに集魚錘を使うよりも有利という局面があるように感じる。セコい話だが、根掛かりが多くて高価な集魚錘を使うのがもったいないというときにも使う。
 形状の差は聞き上げたときに竿先や手元に感じる重さに出る。六角錘だとスッと持ちあがり、丸型だと錘が底を切る直前に重く感じる。聞き上げで底を大きく切って誘いを入れたいときは六角錘を、ゼロテンション状態で魚信を取って魚信が出たら竿先を送りたいときは丸型錘の方が釣りやすいような気がする。でも……そんな繊細な作業、頭では分かっていても腕が付いていかないので、六角錘にするか、丸型錘にするかは気分次第ってことが多い。
形状の差は聞き上げたときに竿先や手元に感じる重さに出る。六角錘だとスッと持ちあがり、丸型だと錘が底を切る直前に重く感じる。聞き上げで底を大きく切って誘いを入れたいときは六角錘を、ゼロテンション状態で魚信を取って魚信が出たら竿先を送りたいときは丸型錘の方が釣りやすいような気がする。でも……そんな繊細な作業、頭では分かっていても腕が付いていかないので、六角錘にするか、丸型錘にするかは気分次第ってことが多い。
最近の釣りのお勉強記事
・夜メバルで来年振り出しに戻らないための内容の薄い備忘録・聞いているタイミングで魚信を出すのが胴突きシロギスの肝
・意図せずクロムツとシロムツの釣り分けに成功してるのだが
・ブラクリの自作は超簡単。でもどうしてPEで作るんだろう?
・ほぼ尺記念♪にイワシメバルのこうかな?メモを残しておく
・フグには海津針。多動性には短ハリス。アマダイ釣り小ネタ
・来年こそは釣りたいな~っと新島キンメのソレダメ!忘備録
・仮説と検証が釣りの楽しみ。カイワリング実験はまだ続くよ
・シロギス胴突きはタルマセ→シャクリだけの方が誘える?
・来年こそ40Upを釣りたい。萬栄丸・半夜クロムツ備忘録
・ウィリー+土佐カブラのハイブリッドでカイワリング2.0に
・本線に結びコブを作らないで強度保つ枝ス三方編み込み改
・良型率100%(今のところ)の土佐カブラのカイワリング
・目標尺超え!! イワシメバル初体験に向け釣り方を調べる
・目指せ半束…エビメバル手返し向上作戦を真剣に考えよう
・ビギナー多数の激混みアジ攻略は短仕掛けと声かけかな
・珍しく二連続で釣れた♪から長ハリスコマセマダイの備忘録
・細ハリスクッションなしイサキはドラグにおまかせが正解?
・群れが出入りする久里浜イサキはタナ決め打ちで粘り強く
・女子のコマセ振りはちゃんと片手をリールの前に添えて2回
・次こそツ抜けを! ヤリイカ釣行1回こっきりの人の備忘録
・初めてのLTアジ(コマセ)釣りで覚えてから行くべき8つの事
・クロムツ釣りは一度目の前にエサを通してから落として誘う
・剣崎イサキが超低活性時にはシャクらない・教えない作戦
・遠征ウィリーで魚種限定なのは枝ス5センチだったせいかも
・眉に唾少なめでOK。へた釣り印のカイワリ実績あり仕掛け
・イシダイの聞き上げは本当に竿を持ち上げるだけでよいのか
・きっとまた行く! 久里浜沖イシダイ五目の釣り方の備忘録
・マダイ釣りでクロダイ釣れたらタナを1メートル上げるが定石
・釣行後ほんの5分のひと手間でPEラインの寿命が半永久に
・災害級の暑さでも元気に釣りできる猛暑対策グッズまとめ
・糸の結び方は3つ覚えておけばマグロ釣らなければ大丈夫
・潮が速い日のアジに名人秘伝の脱力系フワフワ誘いを試す
・カイワリだけを選んで釣れた!! チダイは釣り方分からない!?
・仕掛け強度を上げるため添え糸なし枝ス編み付けを覚える
・動かさないウィリーの方にイサキが食ってくる条件を妄想す
・考えだすとハマるので考えたくはない枝スの長さの最適解
・ヒラメに味を占め来季もきっとやる。八景沖アミ五目備忘録
・潮の速さと仕掛け長、ソウダ禍の相関に悩んだイサキ2018
・剣崎沖イサキでソウダガツオ対策に効果抜群の超短仕掛け
・コマセ釣りは大潮を避ける。流して釣る底棲魚は大潮が○
・初島沖イサキは長ハリスがウィリーより3倍有利と認めるよ
・クロムツ狙いで底からオモリを10mは探る範囲が広すぎた!?
・もう1戦するかっ!! 多動性中年向けオニカサゴ誘い方メモ
・やらないのと知らないのは大違い。マダイの誘い方を調べる
・束釣り記念。えっへんおっほん気分でLTアジ愚策あれこれ
・剣崎沖イサキ2017総括。枝間は50センチ、ハンドルは大事
・イサキの追い食いは仕掛けの張りを意識してゆっくりと巻く
・バルーンサビキに餌が主流? シシャモは7月後半に接岸?
・今秋? 来春?から伝説を始める…深場のこうかな?メモ
著者: へた釣り